「息止めってみんな平均どれくらいできるの?」──子どもの頃に友達と競ったことがある方も多いのではないでしょうか。
大人になって久しぶりに挑戦すると「昔より苦しい」「思ったより短い」と感じることもあります。
実は息止めの能力は年齢や体の状態によって大きく変化するのです。
本記事では、年齢別の平均息止め時間やその変化の理由、さらに息止めを安全に向上させるための方法を徹底解説。
スポーツや健康にも役立つ呼吸法やトレーニングのコツまで、わかりやすくご紹介します。
「息止め力」を知ることは、あなたの心肺機能や生活習慣を見直すきっかけにもなるはずです。
はじめに
「どれくらい息を止められるか?」という質問は、子どものころに友達と競った経験がある方も多いのではないでしょうか。
プールの授業や水遊びのときに「誰が一番長く息を止められるか」で盛り上がった記憶は、きっと多くの人に共通する思い出です。
しかし、大人になって改めて挑戦してみると「昔よりも苦しい」「思ったより短い」と感じることがあります。
実は息止めの能力は、年齢や体の状態によって大きく変化するのです。
本記事では、年齢別の平均息止め時間やその変化の理由、さらに息止めを安全に向上させるためのトレーニング法や注意点について徹底的に解説していきます。
息止めに関する基本情報
息止めとは?そのメカニズムを解説
息止め(ブレースホールド)は、文字通り呼吸を止める行為です。
人間は体内の酸素(O₂)を消費し、二酸化炭素(CO₂)を排出することで生命活動を維持しています。
息を止めると、酸素が徐々に減り、二酸化炭素が増えていきます。このCO₂の上昇が「苦しい」と感じる主な要因です。
実際には酸素が尽きる前に、CO₂の蓄積による呼吸反射が強烈に働くため、長時間の息止めは難しいのです。
平均的な息止め時間の目安とは?
一般的な健康な成人が「何もトレーニングしていない状態」で息を止められる時間は30秒〜90秒程度といわれています。
もちろん体格や肺活量、日常的な運動習慣によって差があります。
一方で、フリーダイビングの競技者などは、トレーニングによって5分以上、トップレベルでは10分以上止められるケースもあります。
つまり「平均時間」はあくまで一般的な指標にすぎず、年齢や習慣による違いが大きいのです。
息止めの能力は年齢によりどのように変化するのか?
子どものころは肺が小さく酸素の貯蔵量も少ないため、息止め時間は短めです。
しかし、遊びや水泳を通じて自然に挑戦する機会が多く「意外とがんばれる」こともあります。
成人になると肺活量が増え、平均して最も長い息止めが可能になります。
ただし30代以降は運動不足や生活習慣によって徐々に短くなる傾向があります。
高齢になると、心肺機能の低下や持病の影響により再び短くなっていくのです。
年齢別の息止め能力
小学生の息止め時間とその特徴
小学生の平均的な息止め時間は20秒〜40秒程度といわれています。
私自身も小学生の頃、友達とプールで「誰が長く潜っていられるか」を競った記憶があります。
その頃は30秒を超えると「すごい!」と周囲に驚かれるレベルでした。
小学生は肺の容量が小さい一方で、新陳代謝が活発で体に酸素を取り込む効率が良いため、意外と粘れる子もいます。
ただし無理をすると水中で危険につながるため、必ず安全に挑戦する必要があります。
中学生の息止め平均時間とトレーニングの影響
中学生になると、肺活量は大きく伸び始めます。
この年代では平均40秒〜1分ほどが目安です。
部活動で水泳や陸上をしている子どもは、1分以上止められることも珍しくありません。
特に吹奏楽部で管楽器を担当している生徒は、腹式呼吸の練習を通じて息止めが長くなることがあります。
この時期はトレーニングの効果が表れやすいため、呼吸法を学ぶと一気に記録を伸ばせるのです。
高校生と成人の息止め時間の比較
高校生から成人にかけては、心肺機能と筋力がピークを迎えるため、最も息止めが得意な時期といえます。
健康な成人の場合、平均は1分前後ですが、運動習慣のある人や歌・楽器をしている人は2分近く止められることもあります。
例えば、私の友人(20代男性・元水泳部)は、練習の一環で2分30秒を超えたことがありました。
一方で、普段運動をしない人は30秒程度しか止められないこともあり、生活習慣が息止め能力に大きな差を生むことが分かります。
高齢者の息止め能力の変化と健康への影響
高齢者になると肺活量の減少、横隔膜や肋間筋の衰え、循環機能の低下などにより、平均的な息止め時間は20秒〜40秒程度に戻ります。
ただし、日常的にウォーキングや軽い運動を続けている方は1分近く止められることもあります。
息止め能力は心肺機能の指標にもなるため、トレーニングを兼ねて無理のない範囲で挑戦することは健康維持に役立ちます。
息止め能力を向上させる方法
効果的なトレーニング方法と呼吸法
息止めを伸ばすには「呼吸法の工夫」と「心肺機能の強化」が欠かせません。
代表的なトレーニングとしては以下のようなものがあります。
- 深呼吸を繰り返し、体内に酸素を十分取り込んでから挑戦する
- 息を止める前にゆっくり吐き切ることで、余分なCO₂を減らす
- 息止めを数回繰り返し、徐々に時間を伸ばしていく
腹式呼吸と深呼吸の役割
腹式呼吸は、横隔膜を使って肺の下部まで酸素を取り込む方法です。
胸式呼吸に比べて多くの酸素を取り込めるため、息止めの前に行うと効果的です。
深呼吸を習慣化することで、自然と心肺機能が強化され、日常生活でも呼吸が楽になります。
水中での息止めトレーニングのコツ
水中で行うときは特に安全に注意する必要があります。
必ず監視者をつけ、1人で行わないことが大原則です。
プールや浴槽での練習では「息を止める時間」よりも「リラックスして行うこと」を意識することが重要です。
緊張すると酸素消費が早まり、かえって時間が短くなります。
心肺機能を高めるための運動と生活習慣
有酸素運動(ランニング・サイクリング・水泳など)は心肺機能を強化し、息止めの持続時間を延ばします。 ま
た、日常的に姿勢を正し、浅い呼吸ではなく深い呼吸を意識することも効果的です。
禁煙や規則正しい生活も、息止め能力の維持に直結します。
息止めのリスクと安全対策
息止め時の身体への影響と注意点
息を止めすぎると酸欠状態になり、めまいや失神を起こす危険があります。
特に水中では「ブラックアウト」と呼ばれる意識喪失が命に関わるケースもあるため要注意です。
頭痛や胸の痛みを感じたらすぐに中止し、無理をしないことが鉄則です。
無理をしないための挑戦と制限
「昨日は1分できたから今日は2分!」と無理に挑戦するのは危険です。
少しずつ時間を伸ばす、体調が良い日に行う、監視者をつける――これらのルールを守ることで、安全にトレーニングができます。
息止め能力とスポーツの関係
アスリートに見る息止め能力の重要性
水泳選手やフリーダイバーはもちろん、サッカーやバスケットボールの選手にとっても「息止め能力=呼吸のコントロール能力」は重要です。
試合中に一気に走り込み、次の動作に移るときに呼吸を整える力があると、パフォーマンスの持続につながります。
スポーツにおける持久力と息止めの関連性
息止めそのものが競技成績を決めるわけではありませんが、心肺機能を強化する一つの目安になります。
長く息を止められる=酸素の使い方が効率的、ということでもあるため、スポーツ選手が積極的に呼吸トレーニングを取り入れるのは理にかなっています。
まとめ:年齢による息止め能力の変化とその対策
健康的な息止め能力を維持するためには
息止めの平均時間は、子どもから大人、高齢者まで大きく変化していきます。
成長期は肺活量が増え、成人期にピークを迎えますが、加齢とともに再び低下します。
日常的に有酸素運動を取り入れ、腹式呼吸を意識することで、健康的な息止め能力を維持できます。
トレーニングの継続とその効果を振り返る
「息止め」は単なる遊びや競争ではなく、健康やスポーツパフォーマンスにも直結する要素です。
年齢に応じた無理のないトレーニングを続ければ、息止めの時間は少しずつ延び、心肺機能も向上していきます。
あなたも今日から深呼吸や軽い運動を習慣にして、「息止め力」を育ててみませんか?

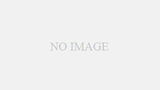
コメント